【基礎ゼミ】第7回〈なぜ、芸術鑑賞に対話が必要なのか〉
【基礎ゼミ】第7回「なぜ、芸術鑑賞に対話が必要なのか」
実施日:2024年7月6日(土)10:30〜15:00
会 場:岐阜県美術館アートコミュニケーターズルーム(以下ACルーム)
講 師:会田大也さん(ミュージアム・エデュケーター/山口情報芸術センター[YCAM]学芸普及課長)
内 容:アート作品と鑑賞者の関係性を考え、作品を鑑賞することから始まる学びやコミュニケーションについて学びます。
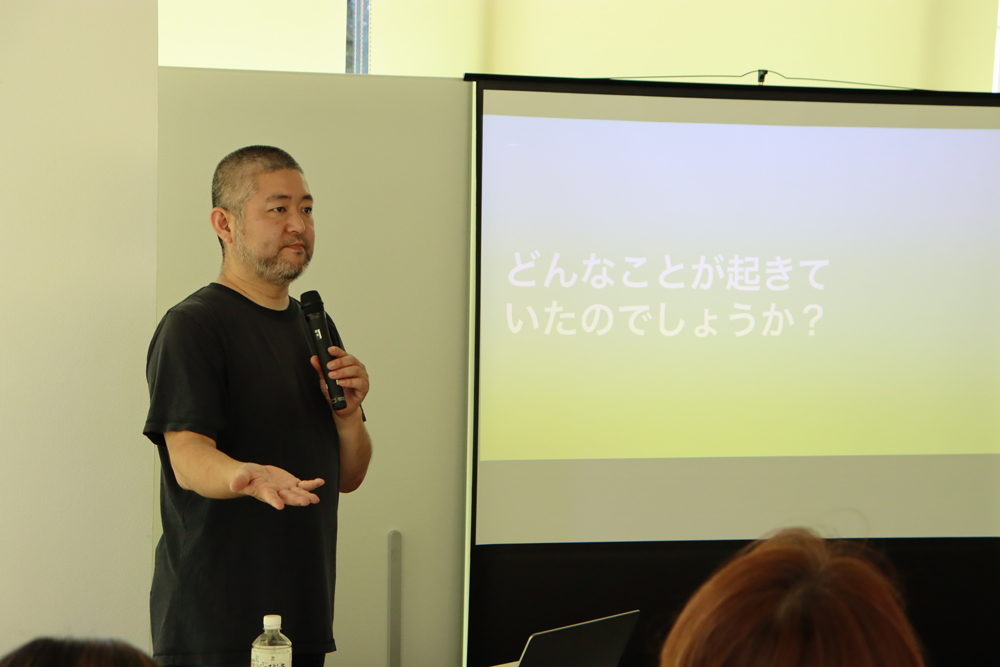
自己紹介
まず、アイスブレイクも兼ねて自己紹介をしました。「でも」や「時々」、「とりあえず」など様々な言葉が書かれたカードの山を引き、引いた言葉を使って話すことがルールです。
思いがけない言葉がでてきて「〜ながラー」は驚いたり戸惑ったりしていましたが、上手に使って自身のことを話し、会場からは感嘆の声や笑いが上がり、空気がほぐれた印象でした。


ブラインド鑑賞
なぜ鑑賞の中で対話をするのか。議題を考えるため、ウォーミングアップとして「ブラインド鑑賞」を実践しました。
2人1組になり、「説明役」と「聞き役」に分かれます。聞き役は目をつむったりスクリーンから背を向けたりして、作品が見えない状況を作ります。説明役はスクリーンに映し出された作品を見て、聞き役に作品の詳細を説明します。聞き役は、説明役の話を受けて質問をし、実際の作品と自身のイメージのすり合わせをしました。




10分間鑑賞したあと、聞き手はスライドに映った作品を確認し、自身のイメージと照らし合わせました。「そういうことか」声をあげたり、イメージと相違が少なく頷いたり、説明役を称えたりする人もいました。
対話しながら鑑賞すると、自分と違う視点を得ることができたり、情報や自身の思考を整理整頓したりすることができます。
実際にブラインド鑑賞をやってみた感想や反省点などを全体で共有し、役割を交代し再度チャレンジしました。
対話型鑑賞 やってみよう
午後からは、会田さんがファシリテーター(司会進行役)を担当し、スライドに映し出された作品で対話型鑑賞を行いました。
30分ほどみんなで鑑賞した後、「どんなことが起こっているでしょうか」という鑑賞中にあった声掛けをキーワードに、ファシリテーターがどのような振る舞いをしていたか、みんなで考え意見を出し合いました。
鑑賞者が発言した内容を言い換えて話し(パラフレーズ)、鑑賞者が新しい視点を持てるようにしたり、作品の画面の話から作者の意図の話まで、議論の段階を変化させる促しをしていた(抽象度のレイヤーを変える)ことを、体験しながら学びました。


また、作品について感じたことは人それぞれで、全て間違いではありません。みんなが自由に発言できる場をつくるため、発言を受けて「そういった見方もあるんですね」「その見方もよいですね」といった声かけで、自由に解釈する余地があると示すことが大切だと学びました。
対話型鑑賞について、作品の手法や作家の詳細のような「外の情報」よりも、目の前の作品から得られる「中の情報」を重視することや、参加する人は様々な人がいて、美術に対する知識や関心も様々であるというお話もありました。


休憩を挟んだ後は、「自由にみる」と題して、みんなで対話しながら別の作品を20分ほど鑑賞し、会田さんのお話やファシリテーターの振る舞い、対話をすることで見えてくる様々な作品等、講義の内容を復習しました。
対話型鑑賞は見る人同士のコミュニケーションであり、作家との対話として見出すこともでできます。
作家の意図を100%理解することはできないけれど、受け手として解釈を生み出すことができる。それは創造的な行為であると学びました。
また、対話型鑑賞でファシリテーターをする際、まずは鑑賞者としての経験を積み「『よき鑑賞者』であることが大切」だと会田さんはお話しされました。
~ながラーのふりかえり
・先生が仰られた「作家の心理をトレースする事は出来ないので、目の前の作品に‘解釈’というアプローチをする」という言葉がとても印象的でした。自分の解釈が作家の意図と違っていると、なんとなく「作品に失礼な事をした」と思ってました。ですが、自分なりの解釈をする事が悪いわけではなく、作品へのアプローチとなるという言葉を聞き、気持ちが楽になりました。これからも自分なりに‘解釈’をして、色々な作品に対してアプローチしていきたいです。
・一つの作品を鑑賞しても、人によって見方はそれぞれで、生活環境、経験などそれらを含めて、見えるものが違うというのは、とても興味深いです。そして、それら全てひっくるめて、新たな視点が生まれるのがとても面白い!!そういった作品を通じて生まれる化学反応を丸ごと楽しめるのがアートの魅力ということを、もっとたくさんの人に知ってもらえるといいなと考えています。
対話型鑑賞は、これから美術館を色んな方に楽しんでもらうための重要なキーワードだと思っています。
スタッフノート
今回のゼミではアート作品と鑑賞者の関係性を考え、対話をすることでより深まる作品鑑賞について、体験を交えて学びました。「~ながラー」として美術館で活動する中で、対話による鑑賞が作品と人を繋ぐ術の一つとして今後の活動に役立てることができそうです。
