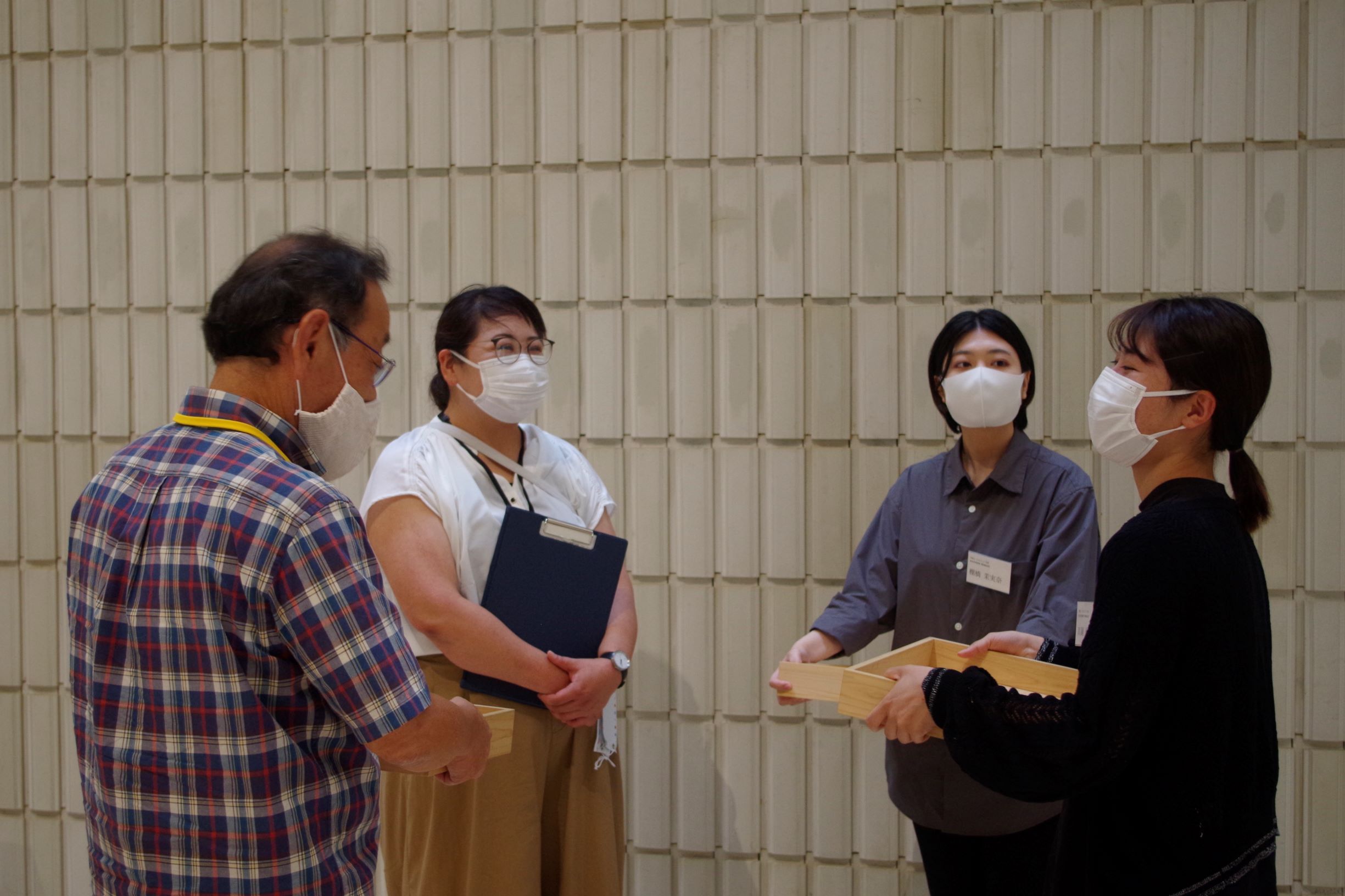こよみのよぶね丸2024
「この舟のろう方式」による活動の記録を、「〜ながラー」の視点からふりかえり、アーカイブとして掲載します。
今回は「こよみのよぶね2024」の企画の様子をお届けします。
【活動期間】2024年6月~2025年1月
【メンバー】
3期:烏野、岸
4期:齊藤結、佃、林、吉田
5期:井川、石原、種田、大堀、岡田、岡本、片之坂、桐山、佐橋、鈴木、馬場、平光、堀部、村瀬、山本
1、活動開始、まずは勉強から
6月23日に第1回ミーティングを実施し、「こよみのよぶね」の歴史やアートコミュニケーターの過去の活動をメンバーで共有しました。
2、スケジュールの設定
7月20日の第2回ミーティングでは、昨年の進め方をふりかえり、今年のスケジュールを検討、年末閉館前に干支行灯を完成させることを目標にスケジュールを設定しました。
3、デザイン開始
9月7日の第3回ミーティングでは、デザイン案を持ち寄り、デザインを概ね決定しました。また、粘土模型を作って竹組のイメージアップに利用しながら、みんなで「龍らしくするには、胴体をくねらせ、玉を持たせ、和紙の輪でうろこを作り・・・」と話が弾みます。
4、こよみ会参加
9月14日に第1回のこよみ会が開催され、これに参加しました。「こよみのよぶね」総合プロデューサーを務める日比野館長をはじめ実行委員会のメンバー、行灯を制作するチームの代表者さん、歴代の実行委員さんが多数集まり、多くの地域の人々と交流できました。日比野館長から「こよみのよぶね」の始まりから今に至る経緯、その意義が語られ、加えてこの秋、岐阜県で開催される国民文化祭に向けて県内47市町村で展開された「ちーオシ」(地域推し活動)との連携に関するお話もありました。
引き続きの「懇親会」は大いに盛りあがり、締めのあいさつは「千年続く祭りの始まりの時期に関わることを誇りに思おう」でした。
5、デザイン変更
実行委員会とデザインやサイズについて調整した結果、舟の安全のため、サイズ制限ありとのことでした。そこで、龍を立たせたデザインに変更、これもなかなかいい感じになりました。
6、モデル作成から竹組開始
デザインを基に3D設計を実施、重心やバランスを考えて3Dモデルを完成させました。
具体的な竹組みの検討を開始、紙の1/5モデルで実際に作ってみると、いろいろアイデアが出ました。
11月になり、竹材料も入手できました。さあ、いよいよ竹組開始です。
まず、胴体のカーブを作りましたが、これがなかなか難しく、治具*を作成し、背と腹の竹をデザイン通りのカーブで固定し、これにあばら骨の竹の輪を固定してから、治具を取り払うという工程で制作しました。
これが案外うまくいき、デザイン通りのスタイルにすることができました。
*治具=工作物を固定し、設計通りの形状に加工しやすくするための工具
また、腕や脚等の比較的小さな部分を作るには竹を上手に曲げる必要があります。
「曲げ」についてはかなり熱心に研究を重ねました。
腕部と脚部の設計からφ200のわっかの組み合わせを基本としました。このわっか作りで効果的だったのがエンボスヒーターの活用です。以下手順です。
①70〜75cmで竹を切断
②エンボスヒーターで曲げ部を加熱
③太もも(曲げ型)に竹を押し当て曲げる
④①と②を何回も全域で繰り返す
⑤わっからしくなったら両端を数cm切断(見栄え良くする為)
⑥わっかの形をダブルクリップで仮止めした後、番線とハッカーで固定
竹を幅方向に薄く出来れば曲げも楽になるはずなので、来年はこの方法についても研究したいと思います。
このような工夫をかさね、竹組は順調に進んでいきました。
7、ニックネームはリュウノスケ
「~ながラー」間でニックネームを募集し、投票の結果、「アシタガワ リュウノスケ」に決まりました。今年一年を振り返る「こよみのよぶね」の日は、来年に思いを馳せる⽇でもあります。明⽇へと続く川を前向きに渡り来年の干⽀「⺒」にバトンをつないでゆく姿をネーミングに込めました。みんなから、「リュウノスケ」と愛着を込めて呼ばれています。
8、行灯制作、和紙貼り&こよみっけ!!イベント
11月末には竹組も概ね完成し、行灯づくりもいよいよ最終段階の和紙貼りです。
12月には「和紙貼り&こよみっけ!!」イベントを開催し、来館者の皆さんとともに「リュウノスケ」に和紙を貼り付け、「こよみっけ!!」*に今年の思い出を描きました。
*「こよみっけ!!」とは1年をふりかえり、大切な出来事のあった月の印とともに、その想いを美濃和紙の短冊に描いたものです。
イベントは大盛況で、多くの家族連れでにぎわい、子供たちも「こよみのよぶね、見に行きたい!」と言っていました。
9、行灯完成、搬出
合計15回のミーティングやイベントを重ね、ようやく行灯は完成しました。
しかし、完成後、灯りを点灯してみると問題が発覚!
腕部と脚部は電球が入っていないので、暗いのです。
何とかならないか?と考えたのが、みんなが「秘策」と言っていた、LEDライトの利用です。色は電球色、狭いスペースに設置出来るサイズ、スイッチのON-OFFが舟上で安全に出来て廉価である事を考慮して2種類のLEDライトを選定しました。
これを当日にリュウノスケの腕と脚に設置することとしました。
本番は予想通り腕部と脚部が映え、秘策を知っている人から「抜群に良かった」と言ってもらえました。
10、こよみのよぶね当日
当日は、実行委員会の指示に従い、以下の通り、早朝から夜までイベントのお手伝いをしました。
・行灯の運び出し、舟への取り付け支援
・巫女及びその付き人の衣装づくり
・プロムナード付近での交通整理
・後片付け、清掃
また、日比野館長にリュウノスケの目を描いていただき、ますます愛らしくなりました。
「こよみっけ渡し」*を行う巫女及びその付き人(竿人という)にも、岐阜県美術館スタッフとともに参加し、無事大役を果たすことができました。
*「こよみっけ渡し」とは「こよみっけ!!」が月毎にまとめられ、「こよみのよぶね」の夜、各月の舟に載せられます。これを「こよみっけ渡し」といいます。
11、左義長
1月14日、長良天神で行われた左義長で行灯と「こよみっけ!!」のお焚き上げを行いました。解体された行灯は和紙の色や残されたパーツにより判別できるものもあり、制作したチームが順に火にくべていきました。行灯を焚き上げた後は「こよみっけ!!」です。「天に舞うよう、天に戻るようにくべていこう」という館長の掛け声に合わせ、500枚超の「こよみっけ!!」を一枚一枚ていねいに火柱に投げ込んでいきました。500人の想いが綴られた和紙が燃され、ふわりと舞い上がると歓声が上がります。こうして全ての行灯、全ての「こよみっけ!!」が「0=ゼロ」に戻り、新たな始まりを迎えることができました。
12、感想
・各チームが一丸となってプロジェクトを遂行していく様子を身近に体験することができ、長年続く伝統のようなものを実感しました。
・イベント当日は急にいろいろな役割を担うことになりましたが、チームワークよく無事に実行することができました。また、実行委員会や他チーム等地域の人々との交流を深めることができました。
・巫女、竿人及びその衣装づくりといった大役をひとりひとりのポテンシャルを活かしながら果たすことができ、「さすが、県美チーム」といった評価もいただきました。美術館と地域をつなげるいい活動であると感じました。
・何もないところから、デザインし、竹と和紙で行灯を作り上げ、壮大なイベントを行えることに感動しました。プロジェクトを通じていろいろな出会いがあり、人と人の縁を感じるプロジェクトだと感じました。
執筆:「~ながラー」烏野、岸(3期)齊藤(結)、佃、林、吉田(4期)井川、石原、種田、大堀、岡田、岡本、片之坂、桐山、佐橋、鈴木、馬場、平光、堀部、村瀬、山本(5期)